2018年09月11日
夫の4人にひとりは離婚後5年以内に再婚している
統計によりますと、離婚後5年以内に再婚した割合は、夫が26.6%、妻が22.1%です。
(平成23年に離婚した者が5年以内に再婚した割合「平成30年我が国の人口動態」政府統計)
夫の4人にひとり、妻の5人にひとりは、離婚後5年以内に再婚しているということになります。
これは総数ですので、年齢別に見てみますと、34歳までに離婚した夫が5年以内に再婚する割合は35%を超えています。35歳~39歳でも29.8%、約3割。
一方、妻は、29歳までに離婚している場合は30%を超え、30歳~34歳で約3割、35歳~39歳で約2割です。
こうしてみると、若い男性ほど再婚する割合が高いということがわかります。
小さいお子さんがいる夫婦がちょうど再婚率が高い年齢層に当たりますから、離婚の面で考えると、養育費の支払いが気になりますね。
離婚後、夫が再婚して扶養家族が増えれば、離婚時に決めた養育費の額が現状に合わない(高い)ということが起こりえます。夫が養育費の減額を要求してくれば、妻は応じなくてはならなくなる。なかなか厳しいですね。
離婚時に子どもの養育費を決めることは最低限行わないといけませんが、妻は養育費をもらいつつも、経済的に自立の道を目指していく必要がありそうです。
養育費の決め方にも工夫が必要。
統計を読んでそんなことを感じています。
2017年02月22日
弁護士を選ぶときに大事にして欲しい基準
【弁護士を選ぶときに大事にして欲しい基準】
離婚にあたって弁護士に依頼しようと考えたとき、知り合いの弁護士がいなくて一から弁護士を探す方は多いです。
そこで私が、弁護士を選ぶときに大事にして欲しいと思う基準があります。
それは、『相性』。 『フィーリング』とも言うでしょうか。
相性ですので、実際に会ってみないとわかりません。逆に言えば、会えばわかります。(もしかすると聴覚が鋭い方は電話で話しただけでピンとくるかもしれませんね)
一度も会わずに、話しもせずにその弁護士に依頼するという方は滅多にいないとは思いますが、これが例えば、友だちや知り合い・親戚に紹介されたとか、前に他の事件で関わったとか、会社の顧問弁護士だとかということになると、話しをする前から、この弁護士にお願いしよう!と決めているケースを目にします。
たまたまその弁護士と相性が良ければOKですが、そうでないときは残念ですよね。その後ずっと一緒に戦っていくわけですから。
ですので、誰かの紹介等で弁護士と会うときは、まず会って話しをしてみて、良かったら契約しようという気持ちで臨む。話してみたけど何となく違和感を感じる…と思ったときは、契約は保留するのが賢明です。『相性』は譲れないところです。
多少の時間とお金はかかりますが、最初から相談料を払うつもりで3つくらいの弁護士事務所に足を運んでみるのがおススメです。法テラスも良いと思います。実際に3つくらい回って話をしてみれば、自分と合う弁護士に出会えると思います。五感をフル活動させて『相性』を確かめてくださいね。
合わない眼鏡をはめて車を運転したら事故を起こす確率が高くなります。同じように、合わない弁護士と一緒に離婚を進めていったら不満の残る離婚になる確率が高くなるかも。ミスマッチが起こると自分も弁護士も実力が発揮できずにもったいないです。ぜひ、相性という基準を大事に弁護士選びを行ってください。
2017年02月09日
面会交流に関係した判例3つ
【面会交流に関係した判例3つ】
先月末はニュースで、面会交流に関係した判例を3つも目にしました。
1つ目は、
父親が別居中の母親に娘を会わせる約束を守らないため、東京家庭裁判所が間接強制として、1回会わせない毎に100万円を支払えという決定を出したというもの。
2つ目は、
離婚後に息子に会わせてもらえなくなったのは元妻とその再婚相手に妨害されたからだとして、熊本地方裁判所が、元妻に70万円、再婚相手には元妻と連帯して30万円の損害賠償金を支払えという判決を出したというもの。
3つ目は、
子どもの親権者を決める裁判で、面会交流の条件が注目されたもので、昨年の第一審では、「年100日母親が子どもに会えるようにする」とした父親が、「月一回程度父親が子どもに会えるようにする」とした母親より、親権者にふさわしいとして父親が親権者とするという判決が出ました。
ところが今回の第二審では、面会交流の条件を重視せず、ずっと子どもと暮らしてきた母親を親権者とするという(第一審を覆す)判決が出ました。
以前から面会交流は子どもの成長にあたって大切なものだということは言われていましたが、平成24年改正の民法に養育費の分担と面会交流が謳われるようになってからは、面会交流をより実現していこうという社会の流れを感じます。
それは裁判所の判断を見ても現れてきていることで、根底にあるのは「子どもの福祉」です。
今後、面会交流を重視した判決が出るにしたがって、離婚後も子どもが離れて暮らす親と定期的に会うことが、アメリカドラマでよく見かけるように、社会の意識として当然のものなっていくかもしれませんね。
とはいえ、離婚後も夫(または妻)とは一切の関わり合いを持ちたくないと考えている方が多いのも事実。
会わせるのが子どもにとっても良いというのは頭ではわかっているんだけど、会わせたくない!という気持ちがどうしても勝ってしまう方。
もしかしたらカウンセリングが有効かもしれませんよ。
2016年12月13日
法務省の「子どもの養育に関する合意書」を利用しましょう
【法務省の「子どもの養育に関する合意書」を利用しましょう】
離婚を考えているご夫婦に良いお知らせです!
本年10月1日に法務省から
『子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A』
というパンフレットが作成されました。
既に各市区町村の窓口で離婚届けをもらいに来た方には配布がされているようですし、法務省のホームページからダウンロードもできます。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
(法務省のホームページより)
「子どもの養育に関する合意書の作成と手引きQ&A」
「面会交流」と「養育費」に関しては、この合意書のひな形を利用すれば、
・夫(妻)に話しをもちかけたいけど、何から始めたらいいのかわからない!
・具体的に何を決めたらいいの?
・何か抜けていることがないか不安…
・専門家に頼むとお金がたくさんかかりそう…
ということがかなり減ると思います。
お子さんがいて離婚をするご夫婦には、ぜひこの合意書のひな形を活用していただきたいと思いますね。
ただ、このひな形に収まりきらない取り決めをする場合や、面会交流や養育費だけでなく他の事柄についても合意書を作りたいという場合には、当然この手引書だけではまかないきれません。
他の事柄も合意書に載せたいというときには、やはり専門家に依頼することをお勧めします。
それともうひとつ大事なこと。
このひな形を利用して「面会交流」と「養育費」について合意書ができあがったら、必ず公証人役場で公正証書にしてもらってくださいね。
2016年12月02日
離婚時の年金分割制度
【離婚時の年金分割制度】
離婚時の年金分割制度は次の2種類
1.合意分割制度(平成19年4月1日から実施)
2.3号分割制度(平成20年4月1日から実施)
どちらも、婚姻期間中の相手方の厚生年金(の標準報酬額)を分割する制度であるため、相手方が厚生年金に加入している必要があります。
(平成27年10月1日に厚生年金に一元化された以前の公務員や私立教職員の共済組合も含みます)
ということは大雑把に言うと、
相手方がサラリーマンであれば年金分割できる!
相手方が自営業者だと年金分割できない!
ということになります。
ただし、サラリーマンであっても小規模個人事業主に雇われていれば厚生年金に加入していなかったり、自営業者であっても会社の役員としてで厚生年金に加入している場合もありますので、そこはやはり自分のケースはどうか?と慎重に調べて判断する必要がありますね。
合意分割制度と3号分割制度には、それぞれ違いがありますが、共通しているのは
離婚をした日の翌日から起算して2年以内に年金事務所に請求の手続きをすること。
年金分割の請求には期限がありますので、段取りよく進めてくださいね。
2016年11月30日
年金分割制度は浸透したか
【年金分割制度は浸透したか】
平成19年4月1日から離婚時の年金分割の制度が始まりました。
制度が始まってから早いもので、もうすぐ10年が経過しようとしています。
(平成28年11月現在)
当時は、離婚するなら平成19年4月1日まで待って年金分割をした方が良いと言われ、結構な話題になっていましたが、最近では年金分割についてさほど話題になることはありませんね。
話題に上がらないのは年金分割制度がこの10年弱で浸透したという良い面があると思います。
けれど一方で、カウンセリングをしていると、年金分割について知らない方がまだまだ多いと感じることも多いです。
今がいくら女性活躍時代とはいえ、夫と妻の収入を比較すればまだまだ妻の方が収入が少ない夫婦が大半だと思います。
夫がサラリーマンであれば、年金分割を請求した方が、妻が将来もらえる年金額が増えるケースが多いです。
(夫が自営業者(国民年金第1号被保険者)では年金分割制度の対象にはなりません)
夫が毎日働いてこれたのは、妻が家庭で家事育児を担ってきたからです。
年金分割の制度ができたこと自体、妻の家庭での仕事が認められたということ。
恥ずかしがらず、面倒がらず、年金分割制度を利用して、将来にわたって自立を目指していって欲しいと思います。
2016年01月05日
明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
事務所&相談室は本日から営業しています。
既に予定が埋まっている日にちもありますが、いつでもお気軽にお問い合わせください。
2015年09月29日
別居している方は注意!マイナンバーの通知
マイナンバー制度がいよいよ始まりますね。
10月中旬から順次マイナンバーが通知されることになっていますが、現在、住民票を移さないまま別居している方はご注意ください!
ひとまず、通知に関して注意すべき点をまとめました。
・ 10月5日現在の住民票の住所に送られてくる
→ 住民票を移せる場合は、今週中といわず一日も早く移してください。市役所の手続きにも時間がかかります。
→ 事情があって住民票を移せない場合は、「居所情報の登録」で実際に住んでいる住所地に宛てて送ってもらうことができます。
ただ、この登録期間が8月24日~9月25日でした。。。 もう終わっています。。。
でも、何らかの対応はしてもらえるかもしれませんので、市役所に聞いてみましょう!
・ 世帯ごと1つの封筒に世帯全員分が入って送られてくる
→ 別居中の夫(妻)に見られたくない方は、自分の実際の住所地で受け取れるように対策を取ってくださいね。
・ マイナンバーには目隠し等の処置はされていない
→ 封筒を開ければマイナンバーが見えてしまう状態らしいので、相手に悪意があればマイナンバーを控えたりコピーを取ったりすることもできてしまいます。住民票の住所地に世帯全員分まとめて届くと困る方は至急対策を取ってくださいね。
別居中の方の中には、少しでも生活費を削ろうとして、新聞を取っていない方もいます。
仕事や家事、育児で、テレビを見る時間さえない方もいます。
標準家庭をモデルケースにして、情報が一番必要な方に届かないまま制度がスタートするわけですから、通知に関してだけでも今後いろんな問題が出てきそうですね。
原則としてマイナンバーは一生その番号を使いますが、他人に不正に用いられるおそれがあると認められる場合は変更ができることになっています。
そのときに柔軟に対応してもらうことが大事になってきますね。
それにしても、いま自分でできることはやっておきましょう!
2015年08月27日
人はいつでも成長途上
大人になってからよく本を読むようになりました。
学生時代は本なんてほとんど全く読まなかったのに・・・です。
本を読んでいると自分の中の知識の広がりを感じますね。
人間、何才になっても成長できる!って思います。
そう考えると、妻が夫を(夫が妻を)
「この人はこういう人!」
と決めつけるのは失礼なことですね。
だって今も成長途上なんですから、もう人間としての枠を固定しまうのは早いというものです。
だから・・・
たとえば、一度相手がミスを犯してしまったとしても、その失敗を糧に大きく成長する可能性もあるということです。
そのミスを、許すか許さないか。
相手に成長のチャンスを与えてあげるかあげないか。
こちらの人間力も試されているような気がします。
人はいつでも成長途上です。
そういう目で見守る余裕も持ちたいですね。
2015年08月21日
相手を責めても自分に返ってくるだけ
望んでいないのに離婚することになってしまったときのショック。
たまらないですね。
やりきれない想い、悲しみ、怒りを、ついつい相手にぶつけたり、相手のせいにしたくなる気持ちはわかります。
すごく傷つき、毎日を生きていく気力をなくしかけているのですから、相手を責めることで何とか今の自分を保っていられるんですよね。
でも、相手を責めても、最終的には自分に跳ね返ってきます。
だから怒りまかせで相手を責めても良いことは全くない。
一時的に気持ちが晴れても、それはほんの一時であとでひどい自己嫌悪に陥る人もいるほどです。
離婚にいたる原因は、どちらか一方が全面的に作り出したということはほとんどなくて、やっぱり夫婦ふたりお互いに作り合いっこしているものなんですね。
そういう前提で、じゃあ自分が作り出した原因って何だろう?って考えてみてください。
結婚生活を振り返って考えてみてください。
その作業は本当にイタい作業だと思います。
でも、踏ん張って、勇気を出して、ぜひやってみて欲しい。
やることで、あなたのこれからの人生がきっと変わってくるはずです。
そして、あなたのその姿勢が周りの人にも良い影響を及ぼすはず。
一番見ているのは誰だと思いますか?
それは、子どもです。
子どもが誇れる生き方を目指したいものですね。
2015年08月12日
2015年07月28日
結婚後5年以内に離婚している夫婦が多い
離婚をした夫婦のうち、3分の1が結婚から5年以内の夫婦
先日、離婚に関するデータを見ていて、あらためて考えさせられました。
5年以内というと、結婚してすぐ!という印象です。
確かに、アツアツの恋愛期間が持続するのは3年間が限度ということも言われていますから、出会いから3年が経った頃に相手に対する想いがスーッと冷めてしまったということは理解できます。
同時に、結婚して(同居して)みて初めて相手のクセやら生活パターンやらが見えてきて、あぁ、この人とはやっていけないわ・・・と思い始めるのもこの期間だということも理解できます。
そうなったら、やり直すなら早い方が良い!ということで、離婚に踏み切るんでしょうね。
(それでも踏みとどまる方も多いですけど)
人生やり直すなら早いほうが良い(実際に何歳になってからでも遅いことはないですが)というのは事実かもしれませんが、結婚後5年以内の夫婦でしたら、子どもが生まれていれば当然まだ幼児でしょう。
そうなると悠長なことは言っていられません。
子どもが独り立ちするまでは親が養育していかなければいけないですから、養育費もきちんと取り決めをしたいです。
精神面でも良い発育が期待できるように、離れて暮らす親とも定期的に会う取り決めもしないといけません。
結婚離婚は本人たちの意志でOKです。
ただ、子どもがいるときは親として責任をもって子どもの成長を一番に考えて欲しいと思いますね。
2015年07月08日
なでしこW杯準優勝!
W杯決勝戦から2日が経ち、ようやく気持ちが上向いてきました (笑)。
なでしこジャパンは強豪アメリカに 2-5 で敗れ、W杯カナダ大会を準優勝で終えました。
連覇を目指していただけに、優勝できなかったことがとても残念ですが、決勝戦を観ると
アメリカめちゃくちゃ強い!
ということを強烈に感じたので、あの決勝戦でアメリカに勝つことは難しかったでしょう。
もちろん最後まで優勝の可能性を信じていましたが。
それにしても、私もかなりダメージを受けました (笑)。
前半15分のうちに4失点ですよ

とくに最初の2点は立ち上がりに立て続けに入れられて、3点目も2点目から10分後、4点目もその直後。
立て直す間もないまま、あれよあれよとゴールが入って、気がついたときには0-4。
ブラジル vs ドイツの 「悪夢の6分間」 が甦ってきました。
サッカーを数多く応援していると、何年かに1度はめちゃくちゃ凹む試合に遭遇します。
去年のブラジルの試合はまだ生傷として私の中に残っているので、今回のなでしこの試合ではダブルの痛み・・・
キツかったです。
それでもね、よくよく思い返してみれば、なでしこジャパンは
W杯準優勝ですよ!
2011年W杯ドイツ大会 優勝
2012年ロンドン五輪 銅メダル
2015年W杯カナダ大会 準優勝
過去3世界大会でメダルを獲得しているということは相当素晴らしいこと。
日本の女子サッカーを世界に示してくれた選手&関係者を尊敬します。
なでしこジャパンが体現してくれた日本女性の良さ
「ひたむき」「芯が強い」「明るい」「礼儀正しい」は、
私たちひとりひとり誰もが持ち合わせている特性だと思うんです。
アスリートだけじゃなく、普通の人にも伝統的に備わっているんですよ。
だからそれを自覚して自信をもって、いろんな困難に向かい合って欲しいなと思います。
大丈夫! あなたならできる!!

2015年06月30日
離婚による影響について、子どもの年齢別考察
『 離婚で壊れる子どもたち 』 の第二章では、離婚による影響について、子どもの年齢別に考察されています。
0か月から18か月児 - 愛着と絆の形成が困難になる
18か月から3歳児 - 親からの分離と個体化が困難になる
3歳児から5歳児 - 離婚は自分のせいだと思う
6歳児から8歳児 - 深い悲しみに陥る
9歳児から12歳児 - グレイゾーンを許せない
13歳児以上 - 離婚体験をプラスに転ずることも可能
見出しだけ引用しました。中身についてはおいおい書いていきたいと思います。
考えさせられたことをふたつほど。
ひとつめ。
乳幼児を抱えて離婚を考えている方がよく言われるセリフのひとつに
「 今なら子どもがお父さんのことを覚えていないから 」
というものがあります。
確かに間違いではないです。悲しいことですが、現実的にお父さんの顔などは覚えていないでしょうね。
お母さんにしてみれば、お父さんという存在がわかってから離ればなれになるのは子どもにとっても辛いから、お父さんを知らないうちに別れておきたい。最初からお父さんはいないということにしておきたい。そういう気持ちが働くのでしょう。
ただそうすると、子どもにしてみれば物心ついたときからお父さんがいない家庭で育つということになり、子どもの中で両親が揃っている家庭というものが存在しないまま大きくなるということです。
いくら母と子で平穏に暮らすことができていても、両親が揃った家族を体験していないわけですから、将来子どもが結婚し家庭を持ったときに戸惑うことになるのではないかと心配になりました。
子どもが小さいうちに離婚をすることになったら、子どもがモデルとなる家族と交流できるように工夫をしていく必要があると思いました。
そしてもうひとつ。
父親との面会交流を継続的に実施していくこと。
子どもが自分の親と触れ合うことで愛されている感覚をもつことはとても大事なことで、自己肯定感や自己信頼感を育むのに役立ちます。これが上手く育たないと、その後の成長に影響が出てくることが多いので、面会交流は頑張って実施して欲しいと思います。
もちろん、母親が安心して子育てできる状態を確保するということが一番大事だということは言うまでもありませんが。
2015年06月29日
『 離婚で壊れる子どもたち 』 を読んで
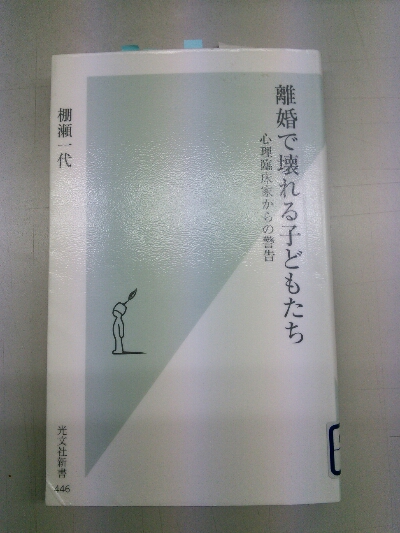
『 離婚で壊れる子どもたち 』
棚瀬一代著 光文社新書
図書館で借りてきてまだ読み終わっていませんが、参考になることがいろいろと書かれているので、自分のためにもまとめておきたいと思います。
「 離婚で壊れる子どもたち 」というタイトルはショッキングですね。
サブタイトルに、「 心理臨床家からの警告 」とあるので、「警告」という意味では目的を果たしているとも思いますが。
日本の法律では、離婚と同時に父か母のどちらか一方を子どもの親権者に定めなければなりません。
結婚中は共同親権で子育てしていたのが、いざ離婚となると単独親権になるわけです。
私たち日本人はこれを当然のことと受け止めがちですが、夫婦の別れが親子の別れに繋がってしいがちな今の日本の状況は、欧米諸国では極めて特異な目で見られているようです。
この本には、離婚によって片親不在となった子どもたちが、幼くして過酷な環境にさらされる中、どう成長し発達していくのか、その軌跡が書かれています。
離婚を考えている方、その中でも特にお子さんをお持ちの方は、子どもから見た「 幸せになる離婚 」を知るためにも、読んでおくことをお勧めします。
また、面会交流がうまくいかない元夫婦(特に同居親)にはぜひとも読んでいただいて、面会交流の大切さを感じていただけるといいなと思います。
2015年06月01日
夫(妻)にもカウンセリングを受けさせたいのですが
相談にいらしたお客さまが、たまに
「 夫(妻)にもカウンセリングを受けに来させたい 」
とおっしゃることがあります。
ご自分が受けたカウンセリングを好評価していただいているということだと思うので、私はとっても嬉しいです。
ただ反面、この言葉どおりに相手側(夫なり妻なり)に来ていただいても、結論から言うと、あまり上手くいくことはありません。
なぜでしょうね?
カウンセリングは、問題意識を感じている本人が「何とかしなくちゃ!」と思って自主的にカウンセリングに来るからこそ、効果があるわけなんですね。
それが 「 相手にも受けさせたい 」という場合、ご本人が思っているほど相手側には問題意識がなかったり、あっても意識に温度差があることが多いです。
しかもほとんどの場合、二人は対立しているわけですから、そんな相手に「行ってみてよ」と言われても、全く行く気が起こらない。
逆にカウンセラーと結託してるんじゃないかと疑われたり、抵抗されてしまったりします。
それでも、何らかの理由で過去にご本人の紹介(?)で相手側がカウンセリングにいらしたこともあります。
が、思ったほど、上手くいくことはほとんどありません。
上手くいかない一番の理由は、ご本人の 『 相手に変わってもらいたい 』 という気持ちが透けて見えているからじゃないかと私は思います。
カウンセリングの場で現れるわけですから、たぶん、それまでの生活の中でも 『 相手に変わってもらいたい 』 という気持ちが日常的に溢れていたと思うんですよ。
相手側にしたら、何だかわからないけど気分が重い・・・ ということなんだと思いますが、それが相手の心を閉ざしてしまっているので、カウンセリングの効果にも影響するのではないかと思います。
その自ら閉ざした心を無理矢理開くわけにはいきませんからね。
こんなことを書いていると、じゃぁ、二人でカウンセリングを受けることは全く意味がないんだと受け取られそうですが、二人で「解決したい」という同じ方向を向いているときには、一緒に来ていただければカウンセリングが手助けできることはあると思っています。
2015年05月15日
いきなり強制執行をかけるよりも
養育費の支払いが滞ったとき、
公正証書(強制執行認諾約款付き)や調停調書があれば、強制執行の手続きができます。
相手がサラリーマンであればお給料を差し押さえて、そこから支払ってもらうのが一般的でしょうか。
強制執行ができると言っても、支払いが滞れば、即、裁判所が自動的に進めてくれるものではありません。
強制執行は、債権者(もらう側)自らが申立をして初めて、手続きが開始されます。
ですので、申立てる or 申立てない は、本人の意志にゆだねられています。
ずっと順調に振り込まれていた養育費。
それが今月は入ってきませんでした。
手元には調停調書があります。
さて、あなただったらどうしますか?
即、強制執行を申し立てるのも良し。
来月末まで待つも良し。
履行勧告をしてもらうのも良し。
内容証明郵便を出すのも良し。
あなたにはいくつかの選択肢があるはずです。
私だったら・・・
まず、手紙を出すでしょうね。 子どもの写真を添えて。
それが功を奏するかと問われれば微妙ですが、いきなり強制執行をかけたときの悪影響を思うと、最初はソフトなアプローチを選択すると思います。( 私の考えですから他の考えももちろんOK )
養育費の支払いは長期間に及ぶことが多いです。
その間、お互い生活環境や価値観等に変化が起こるのが普通です。
きちんきちんと支払ってもらうには、受け取る側の対応も大事だと思います。
嫌いになって別れた相手でも、親として子どもが一人前の大人になってもらいたい気持ちは同じだと思いますので、相手を一人の人間として尊重し、子どもの様子を定期的に伝えるなど、子どもの存在が遠くならないように気を配ってください。
それが養育費をもらい続けるコツのひとつだと言えると思います。
2015年05月14日
養育費が支払われなくなった
「 養育費が支払われなくなった 」
というお話しは、本当によく聞きます。
私も以前は、養育費の取り決めは口約束だった、というケースに何度か会いました。
ですが最近では、皆さんの権利意識の高まりもあり、最低でも書面に残しておかれる方が多くなったように感じます。
なでしこ離婚相談室でも、養育費の取り決めがあるときには必ず強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しています。
公正証書を作成するということは、養育費を支払う側は支払いが滞れば強制執行(給与の差押え)があるということを承知しているということ。
『 給料の差押え 』 が抑止力になって、養育費をしっかり支払っていこうという気持ちが強くなる効果があるんですね。
公正証書でなく、調停調書でも同じ事です。
(調停調書の方がよりメリットがある部分もあります)
ところが、「 養育費が支払われなくなった 」 ケースの中に、調停で合意したものが結構あるんですね。私としては驚きです。
善意で考えれば、よほどの環境の変化があったのかもしれません。
例えば、
お給料が減った
病気になった
親の面倒をみなければならなくなった
再婚した、子どもができた・・・等々。
でも中には、支払うのがバカらしくなった・・・ というように悪意のものもあります。
悲しいですね。
養育費はその名前のとおり、子どもを養育していくために必要な費用です。心身ともに健康に育つためには、お金はどうしてもかかるということは冷静に考えれば理解していただけるでしょう。
親の離婚で一番しわ寄せがくるのが子ども。
支払う側は、離れていても子どもの成長を養育費でサポートして欲しいと願います。
受け取る側は、当然のことと思わずに、毎回感謝を伝える事も大事だと思います。
2015年05月12日
『女性たちの貧困』”新たな連鎖”の衝撃

図書館に行ったときに、たまたま目について気になった本を読みました。
読み始めたら止まらなくなって一気に読んでしまいました。
この本は、NHKの番組制作のために取材した内容を、「番組で紹介することができなかった取材の内容も含めてまとめたもの」らしいです。
若年女性(15歳~34歳)の貧困は、実は親の貧困が子どもへ連鎖しているという事実。
とりわけ、母子家庭の生活の過酷な現実が、取材によって明らかになっていました。
母子家庭、シングルマザーになった経緯は様々です。
離婚もあれば夫の死亡もある。
結婚できずにひとりで子どもを産んで育てているケースもある。
それまでは普通に生活していた女性でも、離婚や夫の死亡を境に母子家庭となり、一気に貧困状態または困窮状態に陥る危うさがあるということが衝撃的でした。
今の日本では、正規雇用で働いている女性以外は、一歩間違えば誰もが貧困に陥る可能性があり、それが子どもの世代にも連鎖していくということです。
DVの世代間連鎖などとも通じるところがありますね。
誰だって、困窮状態や貧困状態に陥ることは望んでいないはず。
セーフティーネットが整っていない今、ひとりひとりができることといえば、安易な離婚はしないこと。
( そもそも結婚するときにしっかりと相手を見て欲しい )
意地の張り合いから夫婦仲が決裂することがないように、お互いに尊重しあい、弱みを見せ合って補いあって、力を合わせて家庭を運営していくこと。
もし夫婦関係が修復不可能で、離婚を選択することになったときには、子どもがいる場合は養育費の取り決めをしっかりとして、払う側はきちんと払う意識を、受け取る側は子どものために大切に使う意識をもつこと。
貧困に関する本をですが、夫婦のあり方について考えてしまいました。
2015年04月24日
相手の気持ちはコントロールできない。だから
相手の気持ちはコントロールできないです。
「こっちはすぐにでも離婚して欲しいんだから早く納得してよ」
というのには無理があります。
「離婚なんて考えられない」という相手の気持ちを、
「離婚OK」に変えるのは、他人には不可能です。
相手の気持ちが変わって欲しいと願うのは自由ですが、変わらないからといってヤキモキするのは仕方ないにしても、イライラしたり他の事が手につかなくなってしまうのは損です。
相手の気持ちはコントロールできないということを肝に念じましょう。
だからといって、じゃあ自分は何もできないのか?というと、そんなこともない。
(相手の気持ちが動き出すことを願って)
いま自分ができることというのは必ずあります。
例えば・・・
服装とか持ち物を替えてみるとか、
断捨離をしてみるとか。
( 本当の思いつきですみません )
相手が離婚に応じてくれない。
いつまでたっても離婚できそうにない。
煮詰まってしまった方は なでしこ離婚相談室 で、あなたが今できることを探してみませんか?


